難産により亡くなった女性が子を求めて生じた妖怪
夜の道端や川べりに、血に塗れた下半身姿で赤子を抱いた姿で現れる妖怪です。「子を抱いてくれ」と、泣きながら赤子を差し出して来て、通行人が赤子を抱くと姿を消します。赤子は次第に重くなり、最終的に石になることもあれば、藁打槌、木の葉に変化することもある。離そうとしても離れず産女に命を奪われることもあれば、重さに耐えてだき続けると怪力を授かることもある。
妊娠した女性が難産により命を落とし、未練を残すことにより生じる妖怪です。産女または姑獲鳥と書き、うぶめと読みます。日本に古くから伝わっていた産女に、中国の姑獲鳥(こかくちょう)が混ざって語られるようになりました。姑獲鳥は夜行遊女や天帝少女などとも呼ばれます。
地域によって様々な伝承が残る妖怪
産女についての伝承は各地域に伝わっており、福島県ではオボ、佐賀県や熊本県ではウグメ、長崎県壱岐ではウンメなど読み方や伝承の最後にも多様なバリエーションが見られます。
日本における産女の最古の記述は、平安時代末期に成立した『今昔物語集』に見られます。巻27第43話にて「頼光郎等 平季武値産女語」にて、源頼光の配下の一人として知られる卜部季武(うらべのすえたけ)が産女に出会った話が語られています。
その他の伝承では、江戸時代の『和漢三才図絵』においても姑獲鳥について触れられていますが、ここでは中国から伝承した姑獲鳥(こかくちょう)に類する解説が主となっています。この本で紹介されている姑獲鳥(こかくちょう)は、女性の姿ではなく実際の鳥の姿となっており、この鳥は、夜に子どもの着物を干すと自分の子どもの着物と勘違いし、目印として妖怪の乳を擦り付けると言われています。羽毛を脱ぐことにより女性の姿に化けることができるなど不思議な力を持った怪鳥です。古代中国の『玄中記』において、姑獲鳥は妊婦が死後に変化したものであり、子を持てなかった無念と恨みから他人の子どもを攫って自分の子として育てるとされます。
.png)
妖怪画に見られる産女・姑獲鳥
江戸時代以降、産女は妖怪画にも多く描かれるようになりました。
鳥山石燕先生の『図画百鬼夜行』には水辺に佇む姑獲鳥の姿が描かれており、その表情からは哀しみや無念が伝わってきます。佐脇崇之先生の『百怪図巻』には、血に塗れた下半身が赤く生々しい色彩で描かれています。月岡芳年先生の『幽霊之図 うぶめ』は後ろ向きの女性の姿が儚げに描かれており、妖怪画というより幽霊画の描き方が全面に出されていますね。
.png)
産女・姑獲鳥(うぶめ)の正体
冒頭にも述べたように産女・姑獲鳥の正体は、難産により命を落とした女性と言われます。一方、山岡元隣先生による『古今百物語評判』の巻二第五では、動物の死骸から虫が湧くように妊婦の死体から生じた鳥が妊婦と同じような行動を取ると述べています。少し飛躍した考えのようにも感じますが、人間の死体に群がる生き物がいれば、不気味な感じがしてもおかしくはないですね。
また、産女の正体について迫るには、この妖怪が起こす怪異とその場所に着目すると良いかもしれません。どの伝承にも共通しているのは、この妖怪が赤子の霊を道ゆく人に渡す、託すという点です。侍や僧、ただの村人と、託される人間に共通点はありませんが、赤子を誰かに負わせることで産女が消えるという点には共通しています。そして、赤子を託され、背負い切ったものには無類の力が手に入るという点も多くの伝承で語られています。特に、秋田県などの伝承ではこのように授かった力をオボウジカラと呼び、他者から見ると手足が四本ずつあるように見えるのだそうです。赤子を背負い切った者に赤子の力が宿り、その霊は現世に留まることができるようになるわけです。もしかすると、産女は、生まれてこなかった赤子の魂を現世に繋ぎ止めるために存在する妖怪なのかも知れませんね。そう考えると無念さや怨みを感じさせる表情は、我が子を現世に留めたいという焦燥や執念の表情なのかも知れません。
加えて、産女の現れる場所が水辺や道端という点も興味深い話です。我が子を現世に留めたいのであれば、生家や血縁の者に託したいと考えるのが一般的ではないでしょうか?それなのに、なぜ産女は家ではない場所に出現するのか。これには現代の日本に生きる私たちには分かりづらい感覚が関係します。昔の日本では、「嫁して三年子なきは去る」という言葉が当たり前のように許容されたり、子を成せない女性のことを「石女(うまずめ)」と呼び、嫁いだ家から追い出したりしていたそうです。女性は新しい生命を生み出す、神秘的で崇高な存在ですが、「子を産めないなら追い出す」という乱暴な考えが一般的だった時代があるようです。
そんな時代背景を考えると、難産により命を落とした女性が亡くなった我が子をよそに託したくなる気持ちもわかるような気がしますね。もちろん、当時の社会通念上、後妻を娶り家を継ぐ子を成すというのが大切だったのは分かります。しかし、今より医療技術の発達していない中、命を賭して出産に臨み、残念ながら亡くなった女性への敬意や弔いの気持ちは持ってほしいと感じてしましますね。もし、そういった考えが一般的であれば、産女という妖怪は存在することもなかったのかも知れませんね。
メディア作品における産女・姑獲鳥
一番有名な姑獲鳥は京極夏彦先生による『姑獲鳥の夏』でしょう。しかし、冒頭に姑獲鳥の伝承が引用されているのみで、本作に妖怪は登場しません。姑獲鳥の伝承を下敷きに、書かれたミステリー作品となっています。昭和二十年代後半の東京を舞台に、妊娠二十ヶ月の女性と失踪した夫にまつわる謎を解き明かしていく話です。
2008年に放送されたアニメ『ゲゲゲの鬼太郎』の65話「呪いの鳥!うぶめが舞う」では、姑獲鳥(こかくちょう)の性質を反映した妖怪が子どもを攫う話となっていました。成人男性よりも大きな猛禽類のような姿が特徴的です。子どものいる家々に爪で刻印をつける様子は姑獲鳥(こかくちょう)が着物に乳を擦り付ける様子に似ていますね。刻印をつけられた子どもが幼児退行するなど独自の解釈も面白いですね。寒さにより亡くした子どもを探し求める悲しい妖怪でしたが、鬼太郎を幼児化させるなど、強力な妖怪として描かれました。
2021年に公開された『妖怪大戦争ガーディアンズ』においては、主人公やその弟を思いやる母性的な存在として描かれていました。安藤サクラさんの演技により母親の愛情を感じさせるキャラクターとなっています。
また、2020年に原作吾峠呼世晴先生、著作矢島綾先生によって出版された小説版『鬼滅の刃 風の道しるべ』にて、風柱になる前の不死川実弥が戦った下弦の壱が姑獲鳥でした。あくまで鬼であるため、妖怪としての特徴は持っていませんが、子を求める姿は妖怪姑獲鳥に通じるものがあるかも知れません。
図録データ
力:1 渡される赤子が重くなるが、産女自体に力はない
知能:3 人の言葉を解するが複雑な思考はできない
大きさ:3 一般的な成人女性と同じ程度、姑獲鳥(こかくちょう)は鳩と同程度
危険度:2 凶悪なものは病気や命の危機をもたらすが、基本的に赤子の重さで人を脅かす程度
特殊能力:3 赤子を抱き続けた人に無類の怪力を与える
遭遇率:日本全国の水辺や夜道に出現するため遭遇率は高い
出現地域:北海道、沖縄を除く日本各地に出現する
.png)


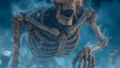
コメント