古くから日本人の間で語りつがれ、現代においてもマンガやアニメに登場し人気の存在である妖怪について
はじめまして、もののけ図録のブログを運営しています。白沢 瑞稀(しらさわ みずき)と申します。本ブログでは、「もののけ」とよばれる妖怪や怪異について紹介し、皆さんからもさまざまな報告や意見をいただくことで、日本各地に伝わる伝承等を蒐集することを目的としています。
蒐集にあたり言葉の定義を定めておくために、最初の投稿をさせていただきました。日本に限らず世界中に「科学では説明がつかないこと」、「古くから語り継がれているが存在がはっきりとしないもの」が、ぼんやりと認識されています。日本においては「もののけ」や「妖怪」、「怪異」、「化け物」、「お化け」と呼ばれる存在です。それぞれのちがいや歴史的な変遷を確認していきましょう。
「もののけ」とは
本ブログのタイトルにも書かれている「もののけ」は、「物怪」、「物の怪」などと書かれ、古くは『源氏物語』や『大鏡』の一説に登場する。当時の貴族らは、もののけが原因で人が病になったり、死亡したりすると考えていた。明確な形を持たず現象としての意味合いが強い。ほとんどの場合、人はこれらの「もののけ」に対応する術を持たず、異常現象の多くが過ぎ去るのを願い、待つことしかできなかった。
「妖怪(ようかい)」とは
現在において一番よく使われる言葉であり、古くは『懐風藻(かいふうそう)』において登場します。はじめは、皆既日食などあまり観測されない気象現象などを表す言葉として使われていたが、やがて明確なビジュアルを持つ存在に使われる事が増えました。そして、江戸時代以降、怪現象に対して人々が「名前」や「見た目」を与えた存在を妖怪と呼称するようになりました。まだこの時は「変化物」や「化け物」と呼ばれることが多かったようです。一般的に「妖怪」の呼称を広めたのは、明治期の宗教哲学者であり妖怪博士として有名な井上円了(いのうええんりょう)先生です。上記の「もののけ」が異常現象など、不可思議なもの全般に対して使われるのに対して、「妖怪」は実像を伴っている点が大きなちがいと言えます。妖怪と呼称される存在は、もののけと比べると、陰陽師や修験者、武士などにより退治、調伏されており、名や姿を言い当てられると力が弱まる怪異の性質を表しているといえるかもしれません。
「怪異(かいい)」とは
古代の日本において朝廷に危機が迫る凶兆として使われてた言葉でした。天皇の住居である内裏(だいり)や寺社における異常な現象を怪異としたが、のちに一般的な場所における異常現象も怪異と呼ばれるようになりました。語源は中国の前漢時代の古典にあり、日本に伝来し使用されるようになりました。
日本における最も古い文献上の記述は『日本書紀』においてみられます。ただし、ここでの怪異は異常気象としての意味合いが強く「妖怪」と同じような使われ方をしています。「妖怪」が異常現象をビジュアル化したもの(天狗)に対し、「怪異」は事象そのもの(天狗礫など)を指すことが多いと言えます。
「その他」の呼称について
「その他」上記の言い方の他に「化け物」や「お化け」、「荒ぶる神」や「悪しき神」などさまざまな呼称が存在し、時代や文化に応じてこれらの存在がさまざまな呼び方で人々に呼称されていた事が伺えます。皆さんは、不可思議な存在に出会った時、どんな呼び方でこれらを定義しますか?

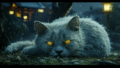
コメント